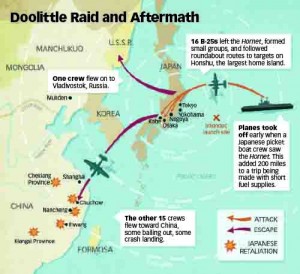〜はじめに〜
私の祖父「N田健吉」は、私が物心がつく頃には既にパーキンソン病に侵されていて歩くのもおぼつかず、表情も乏しく、ボソボソとした喋り方であまり言葉も聞き取れない状態でありました。
それでも私が幼稚園の頃には、祖父の家に遊びに行って囲碁をしたり、日本刀(模造刀?)を見せてもらったり、ほとんど覚えていないけど戦争の話などを聞かせてくれました。
しかし私が中学に上がる頃には病状も進行し完全に寝たきりになり、私はそんな祖父に対してどう接していいのかわからず、時々お見舞いに行く程度で疎遠になってしまったまま、祖父は亡くなりました。
時が経って私も大人になり、歴史に興味が湧いてくると、祖父からもっと戦争の話を聞いておけばよかった、なぜもっと話さなかったのだろうと後悔する様になりました。
そして2015年10月、「南京大虐殺」がユネスコ世界記憶遺産に登録された事により、私は南京大虐殺について必死に調べましたが、事件の本質を掴むことができないでいました。
そんなある日、伯母に聞いてみたのです。
「祖父は戦時中はどこにいたのか?」と。
すると、伯母は一冊の本を取り出し、「掃除してたら出てきたから読んでみなさい」と渡してきたのです。
実は祖父はパーキンソン病を患う前、私が生まれる2年前に「忘れ残りの記」と言う手記を自費出版していたのです。
早速その本に目を通してみると、なんと、祖父は支那事変において南京攻略に立ち会っていたことがわかりました。
私は祖父の手記を頼りに、一兵卒が見たありのままの支那事変を書いてみようと思います。
〜出征〜
私の祖父は、大正7年、熊本の田舎で桶屋を営む両親の元に生まれ、貧しいながらも慈愛に満ちて育てられ、平穏無事に暮らしてきたそうです。
伯母の話によると、貧しさ故に相当な苦労をしたとか。
軍都・熊本が誇る精鋭「第六師団」は満州事変にも出兵しており、祖父が中学の下級生の頃には出征兵士を見送ったこともあったそうです。
祖父は陸軍士官学校への進学を希望し、勉強に励みましたが、何しろ陸軍士官学校は倍率100倍とも呼ばれる超難関校であり、祖父はいささかの自信を持ちながらも入試に落ちてしまいました。
祖父はその後、佐世保の海軍工廠へ採用されましたが、その「一般的には人が羨む職場」を蹴って、陸軍へ志願入隊してしまいました。
本人曰く、陸軍士官学校に落ちたことがショックで情緒不安定だった、とのことです。
祖父が入隊したのは、第六師団 歩兵十三連隊歩兵砲隊でした。
入営したのは昭和12年1月、19歳の事でありました。
入隊して何日かたったある日、班長のA木軍曹が初年兵を集め、「入隊した感想を言ってみろ」と言いました。
初年兵はそれぞれに
「男子の本懐であります」
「お国を守りたいと思います」
と格好いいことを言いましたが、祖父は
「これがまぁ、終の住処かと言う気持ちであります」
と生意気を言ってしまい、祖父は一瞬、殴られるかもと思ったそうですが、荒木軍曹はそれを聞いて
「お前は志願兵だったなぁ」
と頷いておられたそうです。
軍隊にも風流のわかる上官がいることがわかって安心したと語っています。(笑)
剣道をしていた祖父は、その縦のつながりが非常に強く、そのおかげで剣道経験者の上官から気にかけてもらうことも多かった為、
「N田のバックには○○さんがおられる」
と、たびたび上官の名と共に噂になり、恐れられていたそうです。
日々の訓練に明け暮れる毎日の中、昭和12年7月、ついに第六師団にも動員令が下されました。
祖父が配属されたのは第三大隊砲小隊。
動員令が下された事によって赤紙で招集されてきた新兵達が続々と入隊してきました。
この新兵達の中で特にキビキビ働いていた二名は、新婚早々の身であったそうです。
祖父は現役兵であるが故に先頭にたって仕事をし、不眠不休で軍備を整えました。
8月1日、熊本にとっては満州事変以来の出征となる日がやってきました。
支那では国民党軍による日本軍への挑発行為を看過できなくなり、北京、天津を平定する「平津作戦」が7月28日に展開されていました。
同時に北支方面への三個師団の増派も決定していたのです。
兵舎には別れを惜しむ出征兵士の家族が殺到しました。
祖父の父は家に残りましたが、母と姉夫婦、弟の賢一と三郎が、祖父が出てくるのを何時間も待ってくれていました。
 |
| 十三連隊の営門 |
祖父の弟、賢一は祖父の姿を求めて立ち尽くしていましたが、祖父を見つけると走り寄り、そばを離れずに歩き続けました。
この時の兄弟の会話は覚えていないそうですが、おそらく、
「父さん母さんを頼む」というような事を言ったかも知れない、と祖父は回想しております。
流石に親との別れは辛かったそうです。
もともと一種の諦めにも似た感情で入隊したので、旅行にでも行くかのような明るい気分であったそうですが、幼い弟達、そして父母を残して死地に赴くのはなんとも申し訳ないと感じ、未練を断ち切るために祖父は駅までの見送りを断り、水道町までで別れる事にしました。
熊本駅に着くと目に飛び込んできたのは「皇軍万歳」を叫んで見送ってくれる人々の大群衆でした。
本来ならば、ドラマなどでよく見かける、見送る人々の「万歳、万歳」の声援を浴びながらの出征となるのですが、祖父は軍馬を世話するために貨車に残り、その光景を目にする事はできませんでした。
 |
| 熊本駅からの出征 |
列車が動き出すと、「生きて帰ろう」と自分に言い聞かせながら、故郷の空に向かって
「お父さん、お母さん、さようなら」
と敬礼をし続けるのでした。
〜大陸へ〜
熊本駅から列車で小倉まで来た後は、出征兵士は船に乗って移動し釜山に到着、民宿で一泊することになりました。
祖父は早朝に起床し、軍馬に餌付けをしたその帰りに、浴衣姿のT時大佐が一人の兵隊を殴り付けているところを目撃しました。
喧嘩だろうかと駆け寄り、近くの人に事情を聴くと、殴られている兵隊は昨夜民宿を抜け出し女郎屋に行き、その帰りをT時大佐に見つかったという事でした。
「今、我々は戦地に赴かんとしてこの地に立ち寄っているのだ。特に軍規、風紀は厳しくせねばならぬ事は理解できるが、緊張した兵隊の気持ちも理解してやってはどうか」
と祖父は心の中で思ったそうです。
その後部隊は釜山を出発、列車で北上します。
大きい駅では妓生による接待がありましたが、本当に美人が多かったそうです。
 |
| 妓生 |
第六師団は列車で天津を目指しました。
7月28日の平津作戦で北京・天津を一日で制圧したものの、国民党軍はなんと四十数個師団を北支へ増派していたのです。
支那事変が本格化した今となっては、目指すは敵の首都・南京です。
しかし上海から南京までのルートは水路が入り組んでいるため、水田が乾く秋以降まで待たねば進軍が困難でした。
そのため、まずは北支に集結した敵兵力の粉砕が目的とされました。
長い長い汽車の旅が続いた後、8月12日に天津に到着します。
永い貨車での生活で皆、身体中に湿疹ができており、痒いのを我慢して軍装を整えました。
部隊は南開大学というところで宿泊しますが、ここは1904年に開校された、支那では最も早く設立された私立大学でした。
日本軍の爆撃により破壊された箇所もあったようです。
祖父は支那の学生達が勤勉に学んでいることを本棚の教科書などから察し、「祖国愛」がこの国の青年にも芽生えている事を感じました。
清国時代に列強の植民地状態であった支那は、辛亥革命によってナショナリズムを呼び起こされました。
そのやり場のないナショナリズムの矛先が、欧米ではなく日本に向けられた事は非常に残念な事であります。
さて、各部隊は天津警備を命じられ、警備地区内には慰安所も設置されました。
「いつかは死地に赴く」という気持ちでいる兵隊達が殺到しましたが、祖父は分隊長から「君たちは慰安所に行くべきではないぞ」と言われていました。
分隊長は性病にかかり、日本租界に行って注射薬を買い込んでいたのです。
その様を、さながら「軍医並み」だったと祖父は語っています。
分隊長から出鼻をくじかれた祖父は、遊ぶこともできず、勤務外の日は日本人街をブラブラ歩くのがもっぱらの楽しみだったようです。
〜戦場へ〜
人員の増強、弾薬、食料の補給も十分で体力も充実した9月、いよいよ天津を出発しました。
部隊はモロコシ畑の悪路を前進し始めます。
大部隊には国民党軍は近づいて来ないそうですが、祖父は「それでも敵地である、油断は出来ない」と気を引き締めます。
祖父は砲兵であるため、砲車、弾薬車を曳いていかねばなりません。
ぬかるんだ泥んこの道を行軍するときは必ず分隊単位で取り残されるのでした。
祖父は、江津湖や加勢川での悪路突破の訓練を思い出すのですが、ここは戦地の第一線。
体を洗うこともなければ休憩すらありません。
ひたすら歩き続けるのでした。
行き先は永定河、対岸には敵軍の陣地があり、そこを強行突破するとのことでした。
9月14日、祖父は第三大隊砲小隊の渡河地点にたどりつきます。
祖父は堤防に大隊砲の砲座を作りました。
対岸の敵陣地までは1500m。
発射準備を終え周囲を見渡すと、見渡す限りの重火器の砲列に祖父は驚きました。
重機関銃、大隊砲、速射砲、連隊砲、山砲、重砲が60門以上も並び、今や遅しと発射命令を待っているかのようでした。
その静けさの中で、突然ブルブルンと音がしたと思ったら、祖父の近くの工兵隊が作業しているところに敵弾がグワーンと炸裂。
渡河準備をしていた工兵数名が死傷しました。
「あぁ、戦争がはじまるのだ」
と祖父の体に緊張感が満ちてきます。
分隊長の「撃てっ!!」を合図に、祖父は自分が発射した砲弾がどこに命中したのかもわからずに夢中で撃ちまくりました。
大砲の音がまるで機関銃の音に聞こえるほどの砲撃の嵐は壮観だったそうです。
これでいかなる陣地でも完全に壊滅したであろうと思ったものでしたが、日本軍の砲撃が終わって飛び出した小銃小隊に対し、敵は対岸からチェッコ機銃で射撃をバリバリと加えてくるのでした。
 |
| チェッコ機銃 |
祖父は歩兵砲隊であるため、歩兵の前進に遅れてはなりません。
直ちに砲を分解し、部品を抱えて河を渡ります。
少しでも水流に流されでもしたら、重い部品と共に川底に沈むことになります。
祖父は必死で対岸にたどり着くことができました。
急いで歩兵砲を組み立て、逃げ去った敵の後を追います。
初陣でチェッコ機銃をお見舞いされた祖父は、歩兵砲の金具がチャリチャリと音を鳴らしただけで身をかがめてしまう癖がついてしまいました。
後で慣れはしたものの、チェッコ銃の弾が耳をかすめる音は実に嫌なものだった、と語っています。
永定河を渡った次の日、祖父は泥んこになりながらも友軍の後を追いかけていました。
とある村に近づくと何やら物凄い銃声が聞こえてきます。
静かになったので部落に入ると、「日軍歓迎」の旗が立ててありました。
話によると、この村は住民そのものが支那軍の便衣隊であって、この部落に入ってきたS場中尉の部隊を旗を振って歓迎し招き入れ、少数の部隊だと判明すると急に襲いかかってきた、という事でした。
しかしS場中尉はたちまちにしてこれを鎮圧したそうです。
「便衣戦術」とは、支那事変において支那国民党軍がとった戦法で、民間人を装って攻撃を仕掛ける戦術です。
民間人を偽装した戦闘員の事を「便衣兵」と呼び、これは国際法違反の為、捕虜となっても処刑されます。
ハーグ陸戦条約では民兵や義勇兵の交戦資格を認めてはいるものの、「公然と武器を携帯している事」が条件とされており、便衣兵は「犯罪者」として処分されるのです。
支那軍は女子供にまで武器を持たせて、民間人の振りをしては日本軍の背後から攻撃を仕掛けてきました。
日本軍は、誰がどこから攻撃してくるのか、一体誰が敵なのかもわからない恐ろしい戦場で戦っていたのです。
 |
| 女子供でも戦う |
天津で編成された時は不調和の気配があった祖父の部隊も、数日間の戦闘で「死なば諸共」という一致団結の気持ちが作られてゆきました。
そんな中、最初に敵弾に倒れたのは同年兵のH道でした。
畑の中を行軍中に敵襲を受け、祖父の目の前でバッタリ倒れ、そのまま小隊で初めての戦死者となりました。
観測の名手でした。
その後も、かつて練兵場を共に走り回り、世話をしていた軍馬「勇完号」が首を打たれて死亡する別れもありながらも敵の陣地を一つ一つ潰して行きながら行軍し、やがて最終目標は「保定」である事を知らされます。
保定には敵の軍官学校もあり、随分と堅固な城だという事でした。
保定城に近づくと、昼も夜も戦闘が続くようになりました。
保定城の城壁には友軍が波のように押し寄せており、その姿はなんと豪勢な事か、満潮のように敵に攻め寄せていくのです。
祖父は城壁の下に敵陣を発見、これを叩くべく敵前800mの地点にまで前進すると、なんとその先にはすでに観測将校が電話線を引いて観測しているのでした。
それを見て我が軍の砲撃が正確な理由が理解できたそうです。
しかし敵の反撃も凄まじく、祖父は死を覚悟する瞬間もあったそうですが、突然パッタリと攻撃が止みます。
小銃中隊が突入に成功したのでした。
入城してみると、現地住民が日本軍を出迎えてくれました。
敵兵は影も形もなく、退却したのか便衣になったのか、祖父は「見事である」と思いました。
保定市から南下すると滹沱(こだ)河という大きな川が流れており、その対岸には敵軍の大部隊が日本軍を待ち受けていました。
 |
| こだ河 |
十月十日、祖父は小隊長K池中尉に呼び出され、
「気の毒なことではあるが、工兵隊に協力して敵前渡河の準備をしてくれ」
との命を受けます。
これはいわば決死隊であり、命を落とす危険性の高い作戦でした。
指示された場所に行くと、若い兵ばかりが集っており、工兵はすでに鉄舟を組み立てていました。
重い鉄舟を数人で持ち上げ、敵に面している堤防の斜面を一気に駆け下ります。
たちまちにしてチェッコ機銃のお見舞いを受け、だれかが「ウーッ」と声を出します。
次は「ワーッ」と叫び声も聞こえます。
声が聞こえるたびに一人分の負担が肩に食い込んでくるのでした。
水際まで来て舟をジャブンと投げ込めば、工兵がひらりと飛び乗って舟をつなぎ合わせます。
橋を作るようでした。
祖父は剣道の「間の取り方」を戦場で発揮し、敵の攻撃の呼吸を読んでは安全地帯へ帰ることができました。
 |
| 橋を作る工兵 |
友軍の戦闘の結果、滹沱河を悠々と渡ることができた祖父は、次の攻略は「正定」「石家荘」だと張り切っていたのですが、そのどちらも既に友軍が既に占領しており、祖父の部隊は石家荘郊外の「趙県」に駐屯し、警備することになりました。
この辺りの農家では綿花を小屋にうず高く取り込んでおり、祖父は綿花の山の上に寝転ぶのが好みであったようです。
分隊の仲間が見つけ出して来た、土民が隠していたチャン酒を嗜んでいると、程よく酔いが回ってきた同年兵のY沢が歌を歌ってくれるのでした。
綿花の上に寝転んで、彼の体のどこからそんな声が出てくるのか、女性の如き美声が静かに北支の夜空を流れるのでした。
『夏の涼は両国で 出舟入舟八方舟』(曲名・宴かいな)
「女が来とると思った!」
とそっと覗きにくる兵隊、あるいは思わず涙を流して故郷をしのぶ兵もいたわけでありました。
〜杭州湾敵前上陸〜
8月に起こった第二次上海事変以降、上海では日本軍と国民党軍の戦闘が続いていました。
8月下旬には日本からの増援部隊が上海へ上陸しますが、敵兵力は既に30万に膨れ上がっていました。
クリーク(水路)を利用した敵陣地に日本軍は苦しみ、前進できずにいたのです。
さらに敵軍の背後には更なる増援の気配があったため、参謀本部は主戦力を北支から中支へ変更することを決定し、祖父の部隊は北支から抽出されることになりました。
日本は支那での全面戦争など想定していなかったので、一気に増援を送ることができず、全てが後手に回っていたのです。
北支からの増援部隊は、上海を包囲する敵軍の背後をつくため、杭州湾に上陸することになりました。
十月二十四日、全部隊が石家荘に集結。
祖父達は行き先もわからぬまま列車に乗り、塘沽に到着しました。
港には船が待っており、縄梯子をブラリブラリと肝を冷やしながら乗船しました。
兵達は皆一様に「このまま内地に帰りたい」と願ったものですが、その願いは叶いそうにありません。
洋上は見渡す限りの御用船の大群で、周囲には巡洋艦、駆逐艦が警戒の任にあたっていました。
十月三十日、船上で冬服を支給されました。
出征以来、勇猛さを轟かせていたS場中尉(便衣兵の奇襲を鎮圧)は大男であるためサイズが合う軍服がなく、仕方なく裾をチョン切って着ていました。
ある日、「師団長命令、S場中尉は至急司令部へ来たれ」という信号がありました。
S場中尉は
「俺が軍服ばチョン切って着とるとば、閣下が見なさったばい。怒らるるかも知れんバイ」
と怯えていましたが、実際に行ってみると意気揚々として帰ってこられました。
「今度の敵前上陸はS場、頼むぞ」
と言われて上等のウィスキーを賜ったとの事でした。
祖父はこの話を聞いて「さあ、今度はいよいよ敵前上陸だ」と気を引き締めました。
戦友のY沢(歌が上手い同年兵)はどこからかすめてきたのか、小豆の缶詰を持っていました。
甲板の物陰で半分わけして、おいしいおいしいと食べた事は祖父にとって懐かしい思い出となりました。
十一月五日、杭州湾上陸に先立ち、海軍による艦砲射撃が始まります。
聞きなれた陸軍の重砲は、ドーンと発射音がし、シュルシュルと弾道を描き、ドバーンと爆発するのですが、海軍の大砲はドンとドバーンが同時に聞こえるのです。
戦艦の主砲、三十センチ口径から繰り出される砲弾の威力は想像がつかぬ程でありました。
これだけ叩いてもらえばもう安心と思ったのも束の間、意外にも敵の反撃は激しいものでした。
戦闘をする上に於ては、食糧は二の次にしても弾薬は必要です。
祖父は余分なものは全て船上に残し、弾薬を二発身体に巻き付けました。
上陸用船艇に乗り込み、敵弾がピュウンピュウンと飛び交うなか、工兵の運転で海岸めがけて進みます。
しかしまだ海岸の浅瀬にもつかぬのに、工兵が「さあ、飛び込め」と言うのです。
祖父は重い砲弾を二発も背負っているので、万一、足がつかなかったら重りをつけて投げ込まれるのと同じ事になります。
「この野郎!!まぁちっと海岸につきこめ」
と食って掛かると、工兵はビックリして前進してくれました。
船縁からそろりそろりと海中におりると、水深は臍の上までありました。
ずぶ濡れのまま前進また前進。
クリークが張り巡らされ、クリークとクリークの間は湿田です。
一歩一歩あえぎあえぎ前進するも、一時間歩いて振り替えってもまだ何百メートルも進んでいない有り様でした。
どこを目標に進んでいるのかもわからず、ただ海と反対側に向かって歩きます。
祖父は同じ隊のU田さんという召集兵と一緒に、部隊からはぐれてしまいましたが、民家の外れに置いてあった舟に乗ってクリークを漕ぎ進み、無事に友軍と合流する事ができました。
部隊はいつの間にか金山という町に入っていました。
〜南京へ〜
町の中央には綺麗な流れのクリークが、所々に通潤橋のような橋がかかっていて、まるで南画を見ているような思いだったと祖父は回想しています。
敵が逃走する際に火を放ったのか、あるいは友軍が「焼くな、犯すな」の戒を破って火を放ったのか祖父にはわかりませんでしたが、町のいたるところに火の手が上がっていました。
日本軍の悪行として「三光作戦」がよく用いられます。
これは、「日本軍は焼き尽くし、殺しつくし、奪い尽くした」という支那側の主張です。
しかし祖父のいた第六師団には「焼くな、犯すな」の厳しい戒律が存在していました。
さらに支那国民党軍は、「堅壁清野(清野作戦)」という方針をとっていました。
これは自軍が敗走する際、日本軍が物資などを利用できないように村々を焼き尽くすというものです。
支那人が自ら村々に火を放っていたのに、それを「三光作戦」と称して日本軍の所業に仕立てているのです。
祖父が見た火の手は、おそらく支那軍の手によるものだと考えられます。
祖父の部隊は金山の郊外で「大休止」となりました。
大きな民家で休もうとすると、この家にはなんと多くの姑娘(クーニャン・若い娘)が隠れていたのでした。
青木曹長は慌てて
「皆聞け、絶対に姑娘に手を出してはならんぞ!!」
と指示しました。
しかし祖父は、後で泣き崩れていた数人の姑娘を目にしたため、友軍の誰かの手によって若い蕾が散らされたのではないかと考えてしまうのでした。
祖父達は度々現れる敵団を撃破しながら進軍しましたが、十二月に入るとまるで駆け足のような行軍となりました。
他の師団の部隊を道路上でどんどん追い越して行くのです。
祖父の部隊の通過を、道路脇によけて待っていてくれる部隊もあったほどで、皆一様に「第六師団か、なるほど」とうなづいているのでした。
精鋭たる第六師団、一歩でも早く南京城に辿り着かねばならなかったのです。
行軍速度が速いため、補給は間に合わず、大休止となれば先を争って民家から食料を調達せねばなりません。
まず探し出すのはメリケン粉です。これを団子にして、塩と豚肉を入れて沸かした湯にぶち込めば最高の料理になるのでした。
十二月の南京は寒く、祖父が民家の外で膝を抱くように眠っていたら、同年兵のO城君が愛馬の鞍を外し、鞍下毛布を持ってきてくれたので、二人並んで毛布を被って横になりました。
そして朝起きてみると、毛布の上は霜で真っ白になっていたのでした。
祖父達、第三大隊は、南京攻略の時は予備隊とされ、祖父達が寝ている間も第一大隊、第二大隊は激戦を繰り広げていました。
十二月十二日、南京城中華門に通じる道で、大型戦車と共に待機していたら、「万歳万歳」の声が聞こえてきました。
中華門を占領したのです。
首都南京の城は、これまで見てきたものよりも城壁が高く、威容があったそうです。
 |
| 中華門 |
話を聞けば、工兵が爆破した城壁をT越曹長がよじ登り、群がる敵を切り倒し、射撃を加え、たまらんと逃げ出した敵兵を追うように城壁から飛び降りたそうです。
勇将の下、弱卒なし。
曹長の部下達も次々に飛び降りて奮戦し、内側から中華門を開いたとの事でした。
「南京が 12、12と 落ちて行く」
誰が作ったか不明の区が流行りました。
昭和12年、12月12日のことでした。
祖父は南京城中華門を突破した後の事をこう書いています。
「我々は直ちに城内の掃討にかかったが、今や敵兵の姿はなく、南京市の内にはたくさんの市民が残っていた。」
さっきまで戦っていた敵が急に消えるはずがないのです。
逃げ場もなく、国民党軍は軍服を脱ぎ捨て、市民になりすましたとしか考えられません。
俗に言う「南京大虐殺」は、ご存知の通り日本軍が南京に入城してからの2ヶ月間で30万人の市民が虐殺されたとする事件です。
今では「それはおかしいだろ」という声もよく聞かれるようになりましたが、祖父がこの本を書いたのは昭和55年、南京大虐殺という虚構が日本中に浸透しており、「南京にいた」というだけで白い目で見られた時代です。
「日本軍が支那人に対して虐殺行為を行なった!」というプロパガンダが展開されたのは、南京大虐殺が初めてではありません。
1894年、日清戦争の時、アメリカの従軍記者クリールマンによって「日本軍は旅順で冷酷にほとんどの無抵抗の住民を虐殺した。非武装の住民は言い表すことのできないほど切り刻まれていた」と報じられ、国際的に大問題になった事があります。
いわゆる「旅順虐殺問題」です。
しかしクリールマンは米西戦争を煽った張本人と言われるほど過激な「ブッ飛ばし記事」を書くことで悪名が高い記者で、多くの国際学者や公使などが、クリールマンの記事を否定した事で騒動は終結しました。
日清戦争の時、清軍は日本兵を捕まえると過度に残虐な殺し方をしていました。
目や鼻、手足がない遺体が多く、首は切り取られて家屋の軒先にぶら下げられました。
さらには、腹が割かれ内臓の代わりに石が詰められていた遺体もあったのです。
そのような残虐行為をする清兵は、いざ戦局が悪化したら軍服を脱ぎ捨て、旅順の市街地に潜伏し、ゲリラ戦を展開したのです。
日本軍はしっかりと掃討戦を行わねば清兵の手にかかり、自分の命が危ない、それどころか遺体損壊を加えられることをよく理解していました。
そのため、日本軍の掃討戦が行き過ぎた可能性はあるのですが、そうしなければ日本兵は自分の命を守れなかったのです。
日清戦争において、日本は「支那人と戦うということ」をしっかり後世に残しておくべきでした。
「支那人の残虐性」「便衣兵」についての対策をもう少し講じることができていれば、南京虐殺という虚構も作れなかったのかも知れません。
旅順虐殺も、いわゆる南京大虐殺もカラクリは同じなのです。
どちらも支那が便衣戦術をとった事が原因なのです。
確かに、掃討戦の巻き添えを食らった非戦闘員がいたかも知れませんし、便衣兵と間違われて殺された市民もいたも知れません。
しかし私はそれを「虐殺」とは断じて呼びません。
さて、祖父は南京市内に数日駐留しました。
市内を巡回していると学校の校庭に馬が繋がれていました。
捕まえて軍馬にしたいところでしたが、鞍がありません。
そこで誰かが、中華門の門外には軍馬が数頭いたそうだぞと祖父に教えました。
祖父は早速探しに出かけますが、分隊長が「銃を持っていけ」と注意しました。
日本軍は南京城を落としましたが、城外は未だ危険地帯なのです。
城外に出ると、ここにはやはり激戦の跡が残っていました。
土民の食糧と化したか、馬はすでにいなくなっていましたが、鞍がいくつも残っていました。
目的は達したのでいざ帰ろうとすると、何やら城壁下のトーチカで人の気配がします。
そーっとのぞいてみると、拳銃を構えたツンコピン(支那兵)がいたので咄嗟に身を交わしました。
しかしこのツンコピンは負傷しており、すでに拳銃を撃つ力もなかったのです。
かねてよりピストルが欲しいと思っていた祖父はこの拳銃を分捕りましたが、これは「モーゼル銃」であったため重くてかないません。
部隊に帰って分隊長に差し上げたものの、分隊長も一度握っただけで捨ててしまいました。
モーゼル銃とはドイツ製の銃です。
南京安全区国際委員会会長のドイツ人ジョン・ラーべは「南京大虐殺」の肯定派であり、著書「南京の真実」において、「婦女暴行を働こうとしていた日本軍がモーゼル銃を持っていた」と書いていました。
しかしモーゼル銃は日本軍の正規装備品ではないため、基本的には日本兵はモーゼル銃を持っていません。
祖父も分隊長も捨ててしまったモーゼル銃を使いたがる日本兵がどれだけいるのでしょうか?
「婦女暴行を働こうとしていたモーゼル銃を持った日本兵」が本当にいたのかどうか疑わしい限りです。
また、ジョン・ラーべは支那とドイツの通商を仲介し美味しい思いをしてきた人間であり、支那とドイツの仲を切り裂く日本はジョン・ラーべにとっては邪魔な存在であり、決して政治的に中立な人物ではないことを申し上げておきます。
〜蕪湖警備〜
12月17日、祖父の部隊は「南京入城式」を見ることなく、隣の都市「蕪湖(ウーフー)」へと移動を開始します。
 |
| 南京入城式 |
「敵の首都・南京もこれで陥落した。これで敵も降参するであろう。そのうちに蒋介石との間に講和談判が行われ、我々は懐かしの故国に帰れるのであろう・・・・」
という祖父の願いは虚しいものでした。
南京を出発するにあたって祖父は地図を確認しました。
蕪湖は揚子江流域では大きな町のようで、一日の行程で着くだろうと想定しました。
(南京〜蕪湖は福岡〜熊本くらいの距離)
しかし実際に歩いてみると遠いもので、歩き疲れて日も暮れかかった頃、突然、祖父の部隊の数倍もの敵軍が出現します。
いざ戦わんと思った時、「撃つな、撃つな」の声がかかります。
よく見ると、敵に戦意はなくゾロゾロと歩いてくるのです。
投降の意を表しているようでした。
完全武装の敵部隊を武装解除し、やれやれと安心します。
しかし祖父は思いました。
「この人達にとって此処は自分の国である。せっかく山地に隠れていたのになんでノコノコと出てくるのか不思議でしょうがない。教育を受けた直径軍のようだが、食料などの調達が難しかったのかも知れない」と。
「南京大虐殺」がもし真実であれば、この時すでに虐殺は進行しており、日本軍に投降すれば殺されることは容易にわかるはずであります。
しかし現実は、正規軍の大部隊が自らの意思で投降しているのです。
彼らの生活は「日本軍に捕まった方がマシ」と言えるほどだったのでしょうか。
祖父たちはいよいよ蕪湖に到着します。
大隊本部は豪華な家を占領。
祖父の部隊もその近くの宿舎を占領しました。
蕪湖と南京との間にはトラックが盛んに行き来し、揚子江に行けば内地からの汽船も来ていました。
大隊本部の庭には、酒樽や甘味などの加給品が山と積み上げられ、三度の食事も内地米を美味しく食べられるようになりました。
平和がやってきたのではないかと思いたいような日常でしたが、やはりここは日本ではなく、敵国支那の国であります。
蕪湖の周囲には敵の大群が反撃の機会を伺っていたのです。
新聞には華々しく「南京陥落」「蕪湖占領」などと書き立てられますが、実際のところ、上海、南京、蕪湖という点を線で結んでいるだけの状態でありました。
蕪湖から八キロ歩いていくと「山口」と呼ばれるゴーストタウンがあって、ここを防衛戦とし、十日間交替で警備に出ることにしていました。
時として蕪湖の宿舎で安眠しているところを緊急出動の命令が出たりすることもあるほど、付近の敵の動きは活発になっていたのです。
そこで、一大掃討戦が展開され、祖父は連続二昼夜戦い続けました。
夢中で敵を倒しながら進み行き、相当な戦果をあげただろうと周囲をふと見回してみると、回り回って出発地点に戻ってきていたのでした。
そのような戦いがありつつも、内地からの便りも一週間ほどで届くようになっていました。
兵隊達の遊び場所もできました。
共同浴場も開設され、歩哨の後は一風呂浴びるという楽しみもできました。
市場は賑わい、豚の片身が鮮やかに吊るしてあったり、祖父の好物の豆腐も求めることができるようになりました。
日本軍が駐留することで支那の町は平穏と活気を取り戻すことができたのです。
もちろん南京でもそうであった事でしょう。
春めく頃になると、祖父には楽しみができていました。
慰問袋がとりもつ縁、とでも言いますか、祖父の親類の人が日本赤十字の従軍看護婦として
「病院船景山丸」に勤務していたので、同僚を紹介してくれたのです。
その看護婦さんは、自分も従軍の身でありながら、祖父に慰問袋として日用品やお菓子などを送ってくれていました。
やがて、看護婦姿の写真なども送ってくれるようになったのです。
しかしながら、祖父にとっては夢のような話です。
盛んに文通しつつも、未だ見ぬ幻の恋人でありました。
こうなると、早く平和を取り戻したい、そしてその日まで生き永らえねばならないと、祖父はしきりに考えるようになるのでした。
 |
| 慰問袋 |
祖父達の宿舎は大隊本部と道路で隔てられた場所に位置しており、ある時、本部の庭に酒樽が山のように積み上げられているのを覗き見ることができました。
懐かしい熊本の酒「西海」の四斗樽です。
分隊長の実家は西海を取り扱っており、しきりに懐かしがられるので、早速「西海のこもかむり奪取計画」に取り組みました。
大隊本部の衛兵とも内通し、祖父は沖縄出身で酒好きのO城と、同年兵のHと一緒に、深夜に堂々と正門から入り、「おきつうございまっしゅ」と挨拶しながら西海を一本持ち去ったのでした。
しかし、せっかく盗み出したのに、翌日には各中隊に日本酒が配給されるというオチがつきました。
さらに、日本酒をくすねたと噂がたったのか、祖父の部隊には他の分隊からの来客が増え、しばらくは楽しめると思っていた酒はあっという間になくなってしまうのでした。
祖父は他にも、集積所に集められていたリンゴ箱をくすねたりといろいろヤンチャな事をしていたようです。
そのような楽しい生活がある以外の日は、祖父たちは討伐戦を繰り返していました。
遠足にでも出掛ける気持ちで討伐に行くのですが、それでも一度出動すれば悲しいことに幾人かの戦傷死者が出ます。
「鬼神のごとき戦争上手」と呼ばれ、師団長から「頼むぞ」とウィスキーを賜るほどの猛将であったS場中尉は、対岸の敵に狙撃されてあっという間に戦死されてしまいました。
あるときの討伐で敵陣地に突入したとき、そこにあった文書には祖父達の隊長、K池中尉の名前が明記されており、賞金首にされている事がわかりました。
K池中尉もさすがにギョッとしておりました。
支那と日本軍の自由な商業活動は、支那軍の諜報活動を活発化させていたようで、部隊の情報などは詳しく調べられていたようです。
祖父は昭和13年の四月まで蕪湖に駐屯し、警備と掃討に明け暮れましたが、二十三日、住み慣れた蕪湖を後にして揚子江の対岸に渡ることになりました。
その別れの日、まるで戦地に向かう出征兵士のようだったそうです。
姑娘との別れが辛いと泣く戦友もいました。
残留部隊の人々や姑娘は並んで見送ってくれたそうです。
征くものと残るもの、どちらが苦労するかは神のみぞ知ることでありました。
〜行軍〜
蕪湖を発った祖父は、小さい汽船に乗って揚子江の対岸に渡りました。
そして和県、含山城、巣県と次々に占領。
祖父はその快進撃の道中、内地の十三連隊で訓練していた頃の事を思い出していました。
出征前のある時、内務班で忙しく仕事をしていると、「四月生まれの者は講堂に集合」と声がかかったのです。
祖父は四月八日生まれでした。
驚いて二階に飛んでゆけば、四、五名の兵隊が集まっていました。
すると、砲隊長のS吉大尉が各自の湯飲みに自前の水筒から、手づから酒を注いでくださるのでした。
S吉大尉は月初めに、誕生月の兵隊の誕生祝いをしてくださっていたのです。
「皆それぞれの故郷の方向に向かって、父母上にお礼申し上げる」
と言われては、兵隊達は父母恋しさと、隊長の温情に、涙と共に湯飲みの酒をぐーっと呑み干したものでありました。
そして今、今年の誕生日は討伐戦に明け暮れる日々の中で、その忙しさに忘れ去られていたのでした。
巣県から先は山岳地帯になっており、時折石畳の上を歩くこともありました。昔ながらの文明の高さを感じたものでした。
山を乗り越え、河を渡り、畑をつききって進み続けると、立派な城壁が見えました。
盧州城です。
祖父達はわずかばかりの抵抗を受けるも、難なく占領に成功しました。
敵の城を占領する事は、北支戦線の保定占領以来、すっかり慣れっこになっていて、その要領は「敏速、果敢、焼かず、犯さず」という事になっています。
ほとんど逃げる敵との時間の差がなく入城するのですが、常に敵兵の姿を見失ってしまうのでした。
必死で逃げるので、その早さは理解できるとしても、実際のところは直ちに武器を隠して、住民に早替わりしていたとしか考えられないのです。
盧州城でも、占領の次の朝には治安維持会が出来上がって、日軍歓迎を打ち出していましたが、案外にもタバコを悠然とくゆらせていた主要人物こそが支那軍の将校であったのかも知れないのです。
戦地においては、「戦闘員と非戦闘員の区別」をつける事は非常に重要です。
沖縄戦では、民間人と日本軍が同じ地域内で行動したため、米軍は避難する民間人の列に容赦なく機銃掃射を加えました。
ベトナム戦争では、ゲリラ戦術を展開するベトコンに対して米軍は村ごと焼き払い、全滅させました。
戦闘員と非戦闘員が混じっていたら、容赦無く全員殺されてしまうのが普通なのです。
米軍と比較しても、祖父達日本軍は非常に紳士的な対応をしていたのだと思います。
さて、相変わらず祖父達の進撃速度は速く、正規の補給が追いつくはずもありませんでした。
国民党軍が逃げ去った後の村々から食料を手に入れるしかなかったのですが、祖父達はこれを「蒋介石給与」と呼んでいたようです。
米はだいたい、民家の軒先に吊るされているものを拝借し、家庭菜園で作られていたキュウリなどを副食にしていました。
確かに掠奪といえば掠奪かもしれませんが、支那共産党が主張する「日本軍は奪い尽くした」とはあまりにもかけ離れた実態であります。
ある日の未明、大独山から物凄い銃声、砲声が聞こえてきました。
緊急出動となり、現場へ向かうとすでに敵の姿はなく、大独山中腹にある凹地に陣を構えていた友軍の一個分隊が壊滅していました。
昨夜、この分隊は何十倍もの兵力の敵軍に包囲され、弾薬は撃ち尽くし、白兵戦になった末、頭をカチ割られて殺されていたのです。
祖父の部隊を含む第三大隊の数個中隊はいつの間にか大独山を中心に山ぐるみで包囲されていたのです。
それからは、大独山を中心にしてぐるぐる回りながらの激戦が幾夜とも続きました。
ある夜、水田を通過して体制を整えていた祖父の部隊から50m先に敵兵の影が移動しているのが確認できました。
これは囲まれるな、と祖父が思っていると、いきなりチャルメラを吹き鳴らしながら「ライライ」と敵兵が飛び出してきました。
夜であり、射撃準備もしておらず、大隊砲は使えません。
白兵戦となりました。
祖父達は「いざ白兵戦となれば必ず血路が開かれる」という必勝の信念があったそうです。
白兵戦とは、刀剣などの近接用の武器による戦闘のことです。
信じられない事ですが、日本軍は白兵戦が強く、沖縄戦でも体格で勝る米軍に対し、白兵戦では優位に立っています。
どうやら体格で劣る日本人は、伝統の剣術と、敵と刺し違える「覚悟」で敵軍を凌駕していたようです。
現代社会を生きる日本人の私としては「自分がアメリカ人と戦って勝つ」などという事は想像にも及ばない事であります。
祖父を巻き込んだ白兵戦はひとかたまりになりましたが、やがて双方離れ始め、落ち着く事になりました。
危機を脱した、という安堵感が生まれ、喉の渇きに気づくのでした。
蕪湖を出発して以来、和県、含山、巣県、盧州と数々の城を攻略してきましたが、日本軍はその周囲を「面」として支配できていたわけではなく、点と点を線で結んでいただけでありました。
敵兵は、その中で手薄なところを狙って攻勢を仕掛けてきます。
巣県においては、ツンコピンは排水溝を伝って忍び込み、手榴弾を投げ込んでくる有様で、守備隊は毎夜の如く襲撃を受けていました。
「南京大虐殺」などと言われていますが、一体どこにそんな弾薬、武器、そして暇があったのでしょうか。
さて、盧州での戦闘がひと段落すると、補充として新兵が合流してきました。
歩兵第13連隊の快進撃を追うのは相当な苦労だったと言います。
祖父の部隊にも初年兵が数名入ってきました。
ある日、初年兵の砂辺が油を一缶見つけてきました。
夕食には豚肉、野菜などのフライが作られ、粉醤油をかけて美味しい美味しいと皆で食べたのでした。
しかしせっかくのご馳走であったにも関わらず、初年兵達は夜半から嘔吐、下痢を繰り返して苦しみ出しました。
実は、砂辺が見つけてきた油は和紙に塗るための桐油であり、食用ではなかったのです。
苦しみ悶える新兵達をよそに、祖父達古参兵はケロッとしていました。
出征以来、長い悪食に耐えてきたおかげでありましょう。
〜負傷〜
六月、人員の補充、体力の回復も叶ったところで、敵の包囲網を突破する事になりました。
敵軍は日本軍の野砲、重砲、戦車の移動を妨げるため、いたるところに穴を掘って水を貯めており、ぬかるんだ道を昼夜問わず戦闘を繰り返し、敵城を攻め落として行きましたが、心身の疲労は激しいものでした。
雨が続いたせいか、マラリヤにかかる者も出てきました。
T山くんは戦闘中にガタガタ震え始めたので、祖父が「遠山、退がれ」と命じてもT山君は退がらず、気力のみで戦い続けるのでした。
弾薬分隊のH口さんは花札の名人でありました。この激戦の最中、「おーい弾薬」の声に応じて砲側に弾薬をおいたH口さんの頭部にブスッと音がして敵弾が命中しました。
鉄鉢を貫いてほとんど即死でした。
H口さんは炭鉱に働いていた人で、未だ若い奥様と、赤ん坊が可愛い盛りでありました。
潜山を攻撃中、祖父は雨の中を戦っていましたが、雨が止んだ頃、育児村というところで右耳をやられてしまいました。
両手両足に異常はないため、ガーゼを当てて三角巾で固定し戦闘を続けました。
戦闘が小休止すると、他の部隊の軍医さんが通りかかり、祖父は「どうしたのだ」と問われます。
「少し怪我をしました」
と答えると、三角巾を外して検査され、
「自分の大切な部下が負傷したのに、放置しておくとは何事だ」
と小隊長であるK池中尉に叱りつけました。
K池中尉も「すぐに入院させます」と恐縮しておられました。
祖父としては、五体満足であるから休む必要はないが、命令とあらば仕方ない、とでもいう心持ちでした。
祖父は潜山の野戦病院から安慶へと送られる事になります。
安慶は揚子江岸の都会で、野戦病院を抜け出すと、そこは戦争を忘れるほどの賑わいを見せていました。
日本軍のいろいろな機関もあり、飛行場もあり、揚子江には軍艦まで仮泊していました。
それ故、重要施設を狙って幾度となく支那軍の空襲もあったのです。
ある日、「空襲空襲」と衛生兵達が叫んでいました。
敵機は揚子江岸の港を爆撃、1発が御用船に命中したのです。
重症患者が次々と運び込まれてきます。
見た所予備役、後備役の兵隊さん達も多く、「水をください」と唸る者、うめきながらも妻子の名前を呼び続ける者達が、名前も判然としないまま死んでいくのでした。
その悲惨さを目の当たりにして、戦争は現役兵だけでやりたいものだと考えさせられるのでした。
負傷から1ヶ月と少し立った頃には傷も癒え、祖父は戦友が待っている第一線に復帰したいと考え始めていました。
しかし祖父は丸腰でした。
武器を調達せねばなりません。
野戦病院の衛生兵達は戦闘の経験がなく、武器に無関心でありました。
つまり兵器の管理が不十分だったのです。
病院内を二、三回巡り歩けば、歩兵の軍装を一式揃えてしまうことができました。
「原隊に復帰させていただきます」
と祖父は申し出ましたが、軍医さんは
「何、貴様は上海後送になっている。上海で整形してもらう方がいいよ」
と言われました。
祖父にはありがたい話でありましたが、決意していた祖父は退院する事にしました。
祖父は安慶の街に出て兵站部を探します。
「只今、野戦病院を退院してきた者だ。潜山方面に友軍がいるはずだ。前線に出るトラックがあれば便乗させていただきたい。」
と申し出ると、「宿舎で待機するように」と食券を数枚もらえました。
よく見ると、兵站部の連中は実にサッパリしています。
祖父の軍服は泥に汚れたままです。
祖父が軍服を要求すると「食庫に一杯入っている」との事。
倉庫に出かけ「服をくれ」と要求しました。
「俺は負傷したが、たった今退院した。靴も地下足袋も缶詰もくれ」
と申し入れると
「伝票はありますか?」
との返事。
「これから第一線に向かう俺に誰が伝票をくれるか!俺の直属上官は前線で戦っとる、この馬鹿野郎!!」
と怒鳴りつけると、今度は色白でのっぺりとした伍長が出てきて
「ご苦労さんであります」
と、要求するだけの物品を渡してくれました。
祖父はお礼を言いませんでした。
それどころか
「今度来るときは、この倉庫ごと持ってはってくぞ」
と捨て台詞を浴びせたのであります。
皇軍のためになっていない奴らほど、結構な生活を送っていたのが癪に触ったのです。
(最も、兵站も非常に大切なのですが)
待ちわびた「前線に向かうトラック」が出る事になりました。
トラック部隊は「歩兵さん」と言って有難がって便乗させてくれます。
襲撃されたときに頼りになるからです。
彼らに便乗して行ける最終点までたどり着くことができました。
「あの辺が第一線です」
と輜重兵さん達(しちょうへい)が指し示す地点は山岳地帯であって、目測4キロというところでした。
ここまで来たら私一人で行ける、いや、行かねばならぬと思い、輜重兵さん達にお礼を述べてスタコラと歩き出したのでありました。
〜大激戦〜
祖父は原隊と合流すべく歩き続けました。
もう半分は来たかと言う頃、
「コラッ」
と祖父を大喝する声がしました。
「こらーツンコピンばい。色が白すぎるバイ」
と言う声もします。
「俺たい!三砲隊のN田タイ!」
と祖父が叫んだら
「ほんなこったい」
と言いながら小銃中隊の人たちが横の土手から出て来たのでした。
さすが歴戦の勇士、下士哨の動作も上手くなったものだと感心するのでありました。
祖父の原隊復帰を戦友達が喜んでくれたのは言うまでもありません。
ここは五家牌楼という所でした。
高い丘の頂上に望楼があり、監視哨には都合の良いものでした。
ここに大隊砲が一門、敵の方に睨みを利かせています。
砲の前方はすぐ崖になっていて、200m先の山頂には敵陣があります。
山の稜線を辿りながら行き来するツンコピンの姿が肉眼でも確認できるのでした。
野砲隊もそれぞれ砲位置を定め、夜間でも射撃できるように照準を定めていました。
緊迫した警備生活を送っていましたが、どういうわけか陣地を撤収して部隊が集結することになりました。
身軽な小銃中隊はさっさと出発準備をしているのに、祖父の分隊は十数発ぶちかましてから行けという命令が下りました。
夜空にこだまする砲声のうなりを聞いた後は砲を分解して斜面を降ります。
あちこちに懐中電灯がピカリピカリと動いています。
敵兵がすぐ後方を追って来ているのです。
なんとか集合地点にたどり着いた時には、既にたくさんの部隊が集結していました。
「田家鎮要塞」を攻略しないと、揚子江を船が自由に上れないとの事でした。
 |
| 田家鎮 |
祖父達が集結した広済の周囲には敵の大軍がいましたが、さらに田家鎮では蒋介石の直径軍が堅固な陣地を構築していたのです。
しかし、日本軍はこれまで、戦えば絶対に勝って来ました。
上級幹部は今回の敵も大したことはないと考えていたようで、支給された食料や弾薬は1週間程度のものでした。
九月十五日の早朝、指定された地点に集合すると、何やら口論が起こっています。
どうやら同村出身のE濃が、曹長殿に向かって「大丈夫ですから、一緒に連れて行ってください」と喰い下がっています。
祖父が安慶の病院にいた時、E濃は盲腸炎で運ばれて来たのです。
E濃の看病は、軽傷だった祖父の担当でした。
祖父が退院するときは
「俺もすぐ帰るからナァ」
と見送ってくれたものでしたが、今日、祖父の目の前にいるE濃は痩せこけて顔色も冴えていませんでした。
第十三連隊が作戦行動に移るという情報は、入院中の患者にも伝わっており、祖父が退院した後、続々と退院するものが続いたそうです。
E濃は、手術後未だ体力が回復していないのに、勝手に原隊を追求して来たそうでした。
あるいは余病を併発しているのではと思うほど、衰弱している体でした。
祖父は
「E濃、お前の気持ちはわかるが、結局曹長殿にご迷惑をかけることになるから」
と説得したのでした。
陣容を整えて出発し、松山口という所に到着すると、たちまちにして敵軍から包囲されました。
祖父は敵陣に砲撃を加えます。隣に構える山砲隊も攻撃を加えますが、砲手がやられるのが見えました。
その度に攻撃は一時中止されるのですが、味方の砲手交代は非常に敏速なようでした。
歩兵と最後まで協力するのは祖父達、歩兵砲の任務です。
発射する以上は有効弾を射ちたいのです。
砲弾の数が少ないため、祖父は発射弾を節約することにしました。
翌日も死傷者が増えるばかりで一向に先に進めません。
そこで、夜のうちに凹地を通りラクダ山に登って陣地を構えました。
この山の名前は知りませんが、コブが二つあるから「ラクダ山」と祖父達が名付けたのです。
祖父の陣地のそばには松の木が二、三本あり、その下にIIIMGが銃座を構えていました。
 |
| ⅢMGってたぶんこんなの |
K池中尉は熱があるようで、ラクダ山のすぐ下の民家に入って雨露をしのいでいました。
とにかく敵弾が激しく、なんとかして身を隠すだけの壕を掘らねばなりません。
しかしここは岩石の地質、一生懸命掘っても数センチも掘れません。
「なるようになれ」と祈りながら寝転ぶしか他にありませんでした。
IIIMGが火を吹きはじめました。
また敵の来襲です。
「射手交代」と重機分隊長が叫びます。
その度に射手が死んでいるのです。
銃座が狙われるのはわかっていたのですが、傾斜地であるため、陣地が変えられないのです。
機関銃は直接照準であるため敵から丸見えで、敵弾を受けやすいのです。
それに比べて、祖父の歩兵砲は間接照準もできて便利なものです。
九月十七日、雨になりました。
雨には困りました。
友軍の飛行機が援助を行えないからです。
友軍機が敵陣地を攻撃している間は敵陣地は黙っているのですが、雨が降ると全く哀れなものでした。
雨が降っても逃げ込む場所はありません。
山の下の民家は病身のK池隊長や、負傷者が多数収容されており、元気な者達が休養する余地は全くありませんでした。
祖父達は一晩中歩兵砲とともに雨に濡れ震えながら体を寄せ合い、眠りにつくのでした。
次の日も敵の迫撃砲、野砲の砲弾が次々に身近く爆裂します。
しばらくすると敵兵が山肌を埋めるように真っ黒になって斜面を這い上って来ます。
嫌な奴等だと思いました。
ラクダ山の前方のコブには大隊砲第一分隊が陣地を構えていましたが、這い上がってくる敵が意外にも強力で支えきれなくなり、砲を引きずりながら逃げ降りることになりました。
その時、同年兵のS藤がすぐ後ろに迫った敵兵から撃たれて戦死してしまいました。
同年兵のHがS藤を探しに行こうと言います。
敵兵が去った後、斜面一帯は敵味方の負傷者、死者が折り重なっていました。
やっとの思いでS藤を探し出して連れ戻します。
遠くから狙撃されながらも何とか逃げ戻ることができたのでした。
九月二十日、敵の射撃は益々激しくなります。
雨は止みました。
早く友軍機が来てくれるように祈りました。
戦友が炊いてくれた里芋で飢えをしのぎます。
芋畑はいつの間にか敵軍の攻撃目標になっており、芋掘りに出かけて戦死したものが幾人もいたそうです。
又々、敵兵が攻め寄って来ます。
「あそこだ、あそこに打ち込め」
と大隊長が叫ばれます。
分隊長は
「直接照準だ!砲口を覗いて方向を定めろ」と命じられます。
祖父は立ち上がって大隊砲の車輪を回して方向変換しようとしました。
その瞬間、目の前に迫撃砲がグワーンと破裂しました。
砲側にいた者は吹き飛ばされました。
体の右側にガクッと衝撃を感じ体がフワリと浮きます。
目の前が真っ黒になりました。
ハッと気がつくと敵兵が目の前に迫っています。
彼奴等は負傷者を銃剣で刺し殺すのです。
初年兵の誰かが祖父を引きずりながら斜面を降りてくれました。
衛生兵のY山さんがズボンを切り裂いて手当をしてくれます。
Y山さんの話によれば、W辺さん、M本さんは即死でした。
H木、H、祖父は重症、他に誰が負傷したかは把握できませんでした。
敵の攻撃の合間を利用して患者収容所に運ばれることになります。
衛生隊の人々は勇敢に担架を担ぎます。
担架の列にもピューンピューンと敵弾が飛んで来ます。
運ばれる身で申し訳ないことながら、やはり戦闘している方がズーッと気楽であると感じました。
腰のあたりが濡れてくるのは、大腿部あたりからの出血のようでした。
ボーっとした意識の中で、文通のみでまだ会っていない彼女のことが意識のどこかで浮かんだり消えたりするのでした。
担ぎ込まれた民家には、家の周囲にも負傷兵が並べられ、蝋燭の灯りで手術が行われていました。
ガス壊疽が進行すれば足を切断するより他ないとの説明を受けます。
この負傷者の収容所にまで敵襲があるため、輜重兵や軽傷者が銃を手に取り負傷兵を守ってくれるのでした。
同じ合志村出身のW辺達也さんは第7中隊に所属していましたが、手榴弾の破片を顔に受けて負傷していました。
赤チンで真っ赤になった姿で祖父を探しに来てくれ、「カライモ食ってはいよ」と芋を差し出しました。祖父は嬉しく思いました。
九月二十七日、熱にうなされ、日夜夢の中に明け暮れていました。
疲れ切った衛生兵が田家鎮が陥落したと教えてくれます。
あれほど優勢だった敵を一体どうして追い散らしたのか。
祖父の歩兵砲にしても、弾薬はあと二、三発しか残っていませんでした。
あれから一週間どうして戦ったのでしょうか。
おそらく白兵戦の繰り返しだったのだろうと、祖父は考えました。
日本兵は時として、窮地に追い込まれると人外の強さを見せる事があります。
現代に生きる我々日本人は、その強さを理解する術を失っているのではないでしょうか。
〜帰還〜
負傷した祖父は後方へ移送される事になりましたが、その時祖父は信じられない光景を目の当たりにします。
確かに揚子江沿岸で戦ってはいたのですが、あたり一面、湖になっていたのです。
敵さんも思い切った事をしたもので、日本軍の侵攻を食い止めるため、同胞が苦しむ事がわかっていながらも、堤防を切り崩したのであります。
揚子江の濁流は溢れ出して、今まで畑だったところは一変して河になってしまいました。
こうしてできた水路を利用して工兵隊が食料、弾薬を運んで来てくれて、その帰りに傷病兵を野戦病院まで送り届けようという事でありました。
支那国民党軍はこの「揚子江決壊」の他にも、「黄河決壊事件」も起こしています。
その死者は100万人を越え、ほとんどは支那の住民でした。日本軍の死者はたったの3名とも言われています。
国民党軍は自分たちで堤防を破壊しておきながら、「日本軍の空爆で堤防が破壊された」というデマを流しました。
国際的には、「巨大な堤防を爆弾で破壊するのは無理がある」という認識がなされ、支那の嘘は見抜かれました。
しかし各国とも、支那に対する批判はしませんでした。
日本軍は必死に救助活動を行いましたが、救助、復旧作業をする日本兵、現地住民に対して、国民党軍は機銃掃射を加えたと言われています。
はっきり申し上げておきますと、支那事変において、支那人を最も多く殺したのは、日本軍ではなく、支那国民党軍なのです。
さて、工兵の船が揚子江に出ると、そこには汽船が待っていました。
この汽船は戦利品であり、船員は支那人だったそうです。
この船には同年兵の林君も乗って降り、彼は九江で降ろされたために離れ離れになってしまいました。
九江の野戦病院には重症患者が運び込まれましたが、収容能力をはるかに超える負傷兵を抱え込まされたので、手当が十分でなく、死亡したり、悪化したりした患者もいたそうです。
祖父は軽症ではありませんが、命に別状はなかったのでそのまま南京まで送られました。
船は南京の下関(かかん)という所に着きました。
「しものせきだ!」と喜ぶ兵もいたそうです。
トラックに運ばれて市内の病院に運び込まれたのですが、ここには驚いたことに日本赤十字の看護婦さんが勤務していたのです。
実に久しぶりに日本女性に会えたのですが、やはり大和撫子は美しいとしみじみ感じたのでした。
文通と写真のみの、幻の恋人にもいつか会えるという希望も湧いてくるのでした。
祖父につけられたのは「大腿部下腿部砲弾破片創」という病名でした。
南京野戦病院の炊事係の衛生兵さんは至極親切な方で、何を食べたいかと聞いて回るほどでした。
同じ病室の負傷兵で、北海道の炭鉱で働いていたという兵隊は、近くの竹林から竹を切ってきて竹製の松葉杖を作ってくれました。
このおかげで人の手を借りなくても目的の場所に行けるようになり、理髪所にも酒保(兵士相手の売店)にも行けるようになりました。
その方の名前は思い出せませんが、祖父は今も感謝の念を捧げている次第であります。
その後、祖父は上海へ後送となり、長期療養を要する見込みということで内地帰還を命じられたのです。
〜第二の人生〜
昭和十三年十一月十四日、祖父は上海を出発しました。
海上波静かなうちに門司港に着くと、まず驚いたのは歓迎の人の波でした。
門司から小倉に向かってバスが走ります。
なつかしい内地の風景に見とれていると、道路で行き交う小学生から大人に至るまで、祖父達傷兵を乗せたバスに敬礼をするのです。
「ご苦労さんでした」とでも言ってくれているかのようでした。
陸軍病院から父母へ連絡してもらうと、なんと翌日には母親が面会に来てくれました。
一人旅をしたこともなく、汽車酔いもするのに、人に道を何度も尋ねながら、生きて帰った息子に会いにきてくれたのでした。
十一月二十五日、熊本陸軍病院藤崎台分院に転送となりました。
剣道道場「護国館」の恩師、O方武先生は手製のステッキを持ってきてくれました。
大津中学の恩師、T山先生は、教師達からの励ましの寄せ書きを持ってきてくれました。
そして、幻の恋人は、今や現実の恋人として面会に来てくれたのです。
祖父達は結婚の約束をしたのです。(こうして幻の恋人は私の祖母になりました)
入院中、何度も破片摘出の手術を受け、陸軍病院を退院、軍隊から離れる事になりました。
祖父はいささかの淋しさを感じながらも、新しい人生行路のやり直しに希望を持っていました。
祖父が軍隊に入ったのも、大学へ行くお金がないという家庭の事情がそもそもの理由でした。
昭和十五年当時、日本は未だ強国であり、戦争で傷ついた傷痍軍人は大切にされていました。
職業再教育も無料で受けることができたのです。
「大学教育を受けることも、一つの職業再教育であるが、国家は援助してくれるであろうか」
と担当の役人に質問すると、
「先ず入学試験に合格し、入学許可証の写しを県庁に提出すれば、傷兵保護院から学資金が出る」
との回答をもらえたので、昭和十五年三月、九州歯科医学専門学校(今の九州歯科大学)に入学する事ができたのです。
日本の真珠湾攻撃によって大東亜戦争に突入したのはその翌年の事でありました。
祖父と祖母は、再び戦線に呼び出される可能性を担いながらも、結婚し、小倉で暮らしていました。
戦時下での日常生活は徐々に不自由になって行き、社宅を空襲で燃やされたりしながらも、若い二人にとっては人生の中で最高に幸福な時代であったそうです。
しかし昭和十八年十月十四日、祖父の弟、三郎が雲の涯に散華しました。
三郎は少年飛行兵として熊谷陸軍飛行学校に入校し、猛訓練に励んでいました。
卒業も近いある日、祖父は上の弟の賢一と一緒に、三郎に面会に行ったことがあるそうです。
兄弟三人で過ごした楽しい時間は瞬く間に過ぎ、別れの時に校門まで見送りに来ると、三郎は爽やかな笑顔で敬礼してくれたのでした。
しかし後日聞いた話によると、三郎はその後、兄二人を見送るために体操場の水平横木に登り、
振り返りながら遠ざかって行く兄二人が三郎の視界から消えると、今度は中央の塔の上によじ登っては
「兄さん兄さん」
と泣きながら見送っていたのです。
末っ子であり、まだ15歳だった三郎は、少年飛行兵であるという誇りをも捨て、兄二人を追って共に故郷に帰りたかった事でしょう。
飛行学校を卒業し、戦地に赴く前に再び面会したときは、少年の面影を残しつつも人間的にはグーンと成長していたようです。
しかし、「きりもみ飛行」の訓練中、墜落してしまったのです。
「生きていてくれたら」という思いは祖父の心からいつまでも消えませんでした。
 |
後列左から祖父・祖父の弟賢一、祖父姉の旦那
前列左から祖父姉の子供たち、祖母、祖父両親、祖父姉
祖父の隣のスペースには、三郎がいるはずでした。 |
〜おわりに〜
祖父の「忘れ残りの記」を、全て書ききれたわけではありませんが、なるべく本人の言葉を使うように、第三者目線に構成し直して参りました。
祖父は最後に「一応、この辺で筆を置いて、又いつの日か書きつけたいと思う」と締めくくっています。
しかし、その後パーキンソン病を発病し、ものを書くことができなくなりました。
祖父は戦時中の武功によって金鵄勲章を賜りましたが、戦後は「馬鹿馬鹿しい働きだった」と批判を受けたりもしたそうです。
しかし、剣道の腕前にかけてお国のために戦った事は、いつまでも密かに心の誇りとしていたようです。
日本の歴史は「戦前」と「戦後」に分断されてしまいました。
我々日本人は、先祖が何を思い、何をしてきたのかを考えようとせず、現在の価値観で否定ばかりしています。
しかし私は、支那事変がなければ生まれてこなかってし、現在の職業にも就くことはできなかった事でしょう。
先人たちの作り上げてきた歴史こそが、今の自分を生かしてくれている事、そして自分もまた、歴史の一部なのであることを認識していかねばならないと強く思うのです。