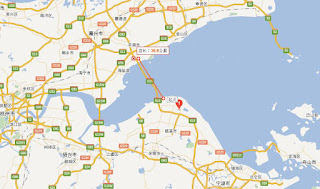|
| 逃げ遅れた支那人の老婆を助ける日本兵(1938 広東省) |
オーストラリア人ジャーナリストで、孫文や蒋介石の顧問として活躍した「ウィリアム・ヘンリー・ドナルド」は、戦後にこう語っています。
「日本は、1938年から1941年までの間に、12回も和平提案を行ってきた。しかもその条件はチャイナに有利なもので、領土的な要求は含まれていなかった。」
 |
| ウィリアム・ヘンリー・ドナルド |
W・H・ドナルドは、1938年以降の和平交渉にしか言及していませんが、その前年である1937年にも日本は何度も和平を模索していました。
1937年8月には「船津和平工作」が進められていましたし、9月にもイギリスを介して和平条件を提示しています。
しかしどちらも実を結ぶことはありませんでした。
10月には、支那に権益を有する九カ国によって、「ブリュッセル国際会議」が開催されましたが、この会議は「日支和平の仲介」が目的とされていたものの、実際は支那利権を有する国々による「日本の吊るしあげ」にすぎず、それを感じ取った日本は不参加を表明します。
日本は「軍事目的が終了した時期に、公平な第三国による和平の斡旋を受け入れる」という方針を決定し、アメリカ やイギリスなどに伝えます。
日本が考えていた「公平な第三国」とは、ドイツでした。
ドイツは支那に領土的な権益を持たず(第一次世界大戦で日本が引き継いだ)、なおかつ「中独合作」によって中華民国との太いパイプを持っていたのです。
ブリュッセル会議の開催など、世界的に和平交渉を後押しする空気の中、日本はドイツ公使の「オスカー・トラウトマン」を仲介した和平交渉「トラウトマン工作」を進め、11月上旬には正式に蒋介石の国民政府に和平条件7カ条を通知しました。
しかし蒋介石は、開催中だったブリュッセル会議でアメリカやイギリスがより強い圧力を日本にかけてくれるだろうと期待して、この和平交渉には乗りませんでした。
このトラウトマン工作は、支那事変の戦線が拡大しきる前の、唯一にして最大の和平の機会であったと言えますが、蒋介石の思惑によって事変の収集には至りませんでした。
以前、中華民国が幣制改革を行う時、イギリスが日本に共同出資を持ちかけ、日本がそれを断り、決定的な溝を作った事を書きました。支那事変7 紙幣戦争
しかし、この支那事変に至っても、イギリスは少なからず日本の味方でいました。
ブリュッセル会議において、イギリス大使は本国政府に「日本に対する制裁を議論すべきではない」という旨を上申していたのです。
イギリスは、列強国が集団で日本に圧力をかけて停戦に持ち込むのではなく、あくまでも日本と支那の問題として、第三国を介して和平を結ぶのが望ましいとする日本の考えに理解を示していたのです。
支那において最大の利権を得ていたイギリスは、アメリカの進出を警戒して日本と歩調を合わせようとしていたようにも思えます。
もし、この時に日本が「国際社会の中で孤立せずに強かにやりこなす」という選択肢を持っていたとすれば、その鍵はイギリスが握っていたのではないでしょうか。
しかし、日本が選んだ道はあくまでも、「列強国によるアジア支配に啖呵を切る」というものでした。
その選択を「愚か」だと断じる事も避けたいと思います。
トラウトマン工作が決裂した日本は、ブリュッセル国際会議の最終日の11月15日、アメリカのグルー大使に
・これ以上支那を追撃する必要はない
・この時期に和平を結ぶのは支那自身の為になる
と訴えかけ、アメリカが和平の斡旋をして欲しいと依頼しました。
当然ながら、アメリカがこの依頼に動くはずもなく、日本軍は南京攻略へと進んでいくことになります。
そして12月、今度は蒋介石が日本との交渉を望んだ為、再びトラウトマンを介した和平工作が行われましたが、すでに日本軍も南京を陥落させて軍事的優位に立っており、さらに多大な損害を被っていた為、それまでのような寛大な条件を提示することはできなくなっていました。(第二次トラウトマン工作)
蒋介石は曖昧な返事でのらりくらりと回答を引き伸ばし、結局両国代表の面会もならぬまま、1938年1月16日、日本政府は交渉打ち切りの声明を出してしまいます。
近衛文麿首相は、「国民政府を対手とせず(国民政府は相手にしない)」と発言し、両国の外交官は帰国、日本と国民政府の国交は断絶されてしまいました。(第一次近衛声明)
両国の和平に奔走した広田弘毅外相は、戦後の東京裁判で「支那事変を拡大させた」としてなぜか絞首刑に処される事になってしまうのでした。
どうすれば終わるのか、いつになったら終わるのか、全く見当のつかない状況の中で、近衛内閣は1938年4月1日、「国家総動員法」を制定しました。
これによって、国家が人的・物的資源を自由に統制できるようになり、国民の自由意志よりも国家の命令の方の優先される事になりました。
この目的は、「長期化する戦争を乗り切る為に全ての国力を軍需に集中させる事」だったのですが、その発想の根本には「社会主義思想」が見え隠れしていました。
国家総動員法を立案したのは内閣直属の「企画院」ですが、実は企画院内部には共産主義思想が蔓延しており、のちに企画院関係者21名が治安維持法違反で検挙される「企画院事件」が起こっています。
「右傾化すると戦争になる」などと報じて現在のマスコミは「右翼=軍国主義」と言うイメージを刷り込もうとしていますが、日本の戦争体制を築き上げたのは「左翼思想」であったという事実も念頭において頂きたいものです。
さて、首都・南京を攻められて「漢口」まで逃げ出していた蒋介石でしたが、日本軍が漢口にまで攻めてくると今度はさらに内陸部にある「重慶」へ首都を移しました。
蒋介石は日本を広大な大陸に引き込んで「消耗戦」を挑んできたのです。
しかし商工業の要所を抑えられた国民政府に、長期戦に耐えうる国力などなかったはずです。
実は蒋介石は、アメリカ・ソ連・フランス・イギリスなどから多大な軍事支援を得ていました。
支那における軍事行動は、支那利権を持つ欧米列強各国を全て敵に回してしまったのです。
支那事変の実態は、欧米列強が背後に隠れた「代理戦争」であったと言えます。
1938年10月、日本軍が要衝「武漢三鎮」を攻略したところで支那事変の戦況は小康状態に入りました。
重慶は山脈に囲まれた要衝となっており、陸軍が侵攻するのが非常に困難だったのです。
ところで、支那事変において世界を敵に回した日本でしたが、理解者がいないわけではありませんでした。
ローマ法王の「ピウス11世」です。
ピウス11世は日本の軍事行動を支持し、
「日本の行動は、侵略ではない。日本は支那を守ろうとしているのである。日本は共産主義を排除するために戦っている。共産主義が存在する限り、全世界のカトリック教会、信徒は、遠慮なく日本軍に協力せよ」
という声明を全世界のカトリック教徒へ発信しました。
ピウス11世は、平和を乱しているのが共産主義である事をいち早く見抜いていたのです。
しかし、第二次世界大戦が始まる前、1939年に死去したため、その影響力を発揮する事はできませんでした。
蒋介石率いる国民革命軍は、日本との戦いの中で多くの一般市民を巻き添えにしてきました。
「堅壁清野」という作戦については前回も書きましたが、これは国民革命軍が退却するときに、日本軍が施設を利用できないように村々を焼き払う事です。
その最たるものが「長沙焚城」です。
1938年11月、日本軍が迫る「長沙」において、「日本軍が来たら火を放つように」と指示をされていた国民革命軍は、長沙城外で火事が起こったのを「のろし」だと勘違いし、次々に放火を始めました。
長沙城内では大火災が起こり、20万人以上の死者が出る大惨事となりました。
他にも、国民革命軍は、日本軍の侵攻を食い止めるため、蒋介石の承認を得た上で黄河の堤防を決壊させました。
これによって黄河の水は堤防の外に流出し、少なくとも数十万以上の水死者が出ました。(一説には100万人とも)
日本軍には犠牲者や損害はほとんどなく、むしろ積極的に現地支那人の救助活動を行なっていたようです。
日本軍と住民達が共同で防水作業をしている所に、国民革命軍は容赦なく攻撃を仕掛けました。
また、国民革命軍は黄河のみならず、揚子江でも同じように堤防を決壊させて大規模な水害を起こしています。
このような国民革命軍の蛮行は、支那の住民達からの反感を買い、国民党の求心力は失われていくことになり、後に共産党に支那の覇権をとって変わられる原因となるのです。
さて、戦況が膠着した後、日本が攻略した地域では治安が維持されるようになり、自治政府ができるようになりました。
国民党のナンバー2であった「汪兆銘(おう ちょうめい)」は、支那事変における国民革命軍の横暴によって苦しむ民衆の被害に心を痛め、日本との和平を望むようになります。
「長沙焚城」を明確に批判した事によって、蒋介石との溝は決定的になっていました。
一向に事変収集の目処が立たない近衛内閣も「国民政府を対手とせず」という近衛声明を修正し、11月3日に「第二次近衛声明」を発表します。
この声明は、欧米に対抗すべく日本・支那・満州で経済ブロックを形成しようとする、アジアの自存自衛の為の構想「東亜新秩序」を謳ったものでした。
この声明に呼応した汪兆銘によって、汪を支持する高宗武(こう そうぶ)などが日本政府と話し合いを重ねるようになり、ついに11月20日に「満州国の承認」「日本軍の2年以内の撤兵」などが約束された「日華協議記録」への調印が実現しました。
これを受けて、汪兆銘は国民党から命を狙われながらも重慶を脱出します。
しかし近衛首相は、12月22日に「善隣友好」「共同防共」「経済提携」の「近衛三原則」を発表し、支那との和平方針を示し「日本軍の撤兵」を外してしまいました。(第三次近衛声明)
この声明の中に、「日本軍の撤兵」が含まれていなかった事に汪兆銘は失望を隠せず、さらに近衛文麿首相は、第三次近衛声明の数週間後に突然総辞職してしまいます。
近衛内閣の後を継いだのは「平沼騏一郎(ひらぬま きいちろう)」を首相とする平沼内閣です。
平沼内閣による汪兆銘との交渉は、近衛内閣と比べ物にならないほど過酷な内容で、汪の側近の高宗武が逃亡して交渉原案を暴露するほどでしたが、汪兆銘は和平を開く覚悟を以って日本の修正案を受け入れ、日本軍の保護のもとで1940年3月に「南京国民政府」を樹立させました。
しかし汪政権である南京国民政府の誕生にも関わらず、日本や汪兆銘が意図したように、蒋介石の「重慶国民政府」との和平実現に繋がる事はなく、南京国民政府は国際的には「日本の傀儡政権」に過ぎませんでした。
汪兆銘は過去に狙撃された時の傷が原因で1944年に死去する事になります。
命をかけて日本との和平を模索した汪兆銘は「漢奸(売国奴)」とみなされ、墓を爆破されて遺体を燃やされ、野原に捨てられてしまいました。
汪兆銘は墓を爆破された代わりに石像が建てられましたが、この石像は弔いの意味を持つものではなく、「唾を吐きかける」為でした。
「死者に鞭を打つ」という文化には、全く理解の余地がございません。
汪兆銘政権も和平には結びつかず、重慶政府との交渉も停滞する状況においては、蒋介石に降伏させるしか事変を終わらせる方法はありません。
しかし重慶への道のりは遠く険しく、陸軍の進軍は困難であるとされました。
そこで航空機による爆撃で重慶国民政府の戦略中枢を破壊する事になり、1938年から1943年にかけて218回の爆撃が行われました。
この爆撃による死者の総数は1万人を超えるとされており、現代においては「無差別爆撃の原型」だと非難され、後に日本全土が空襲で焦土化された事も「重慶爆撃の報い」などと考える人(NHK)もいます。
日本軍の資料を公平な目線で紐解いてみれば、初期の爆撃は間違いなく「無差別爆撃」ではなく、「戦略爆撃」であり、爆撃対象は飛行場や軍事施設に限られていました。
しかし重慶には市街地に相当数の高射砲が設置されており、日本軍爆撃機にも多大な損害が出ていました。
その為、1940年の後半からは市街地を5つに区分し、地区別に絨毯爆撃を行うことになったのです。
日本軍は律儀にビラを撒いて爆撃予告をしていた為、大した戦果は得られなかったようです。
当時の重慶の人口は100万人、218回の爆撃で1万人の死者が出ていますが、これを日本の同規模の都市が受けた空襲の被害と比べてみると、「熱田空襲」では一回の空襲で2000名、神戸では二回の空襲だけで8000名、横浜では一回の空襲で一万人が死亡しています。
数字だけを見ても、日本軍が行った重慶爆撃と、アメリカが日本に行った空襲とでは、「やり方そのものが全く違う」のだと認識できます。
「日本が先に無差別爆撃を行ったのだから、空襲を受けたのは因果応報だ」というような論調には全く同意できないのであります。
1940年、最大速度・武器・航続距離・上昇機能・旋回性能、全てにおいて外国の一流機の水準を超えた戦闘機が開発されました。
その機体は、皇紀2600年の「00」にちなんで「零式艦上戦闘機(零戦)」と名づけられます。
それまでの戦闘機では航続距離が足らず、重慶まで爆撃機を援護することができずに多大な損害を出していた日本軍爆撃機も、零戦によって護衛される事になりました。
零戦の初出撃は非常に華々しい戦果をあげる事になります。
重慶で待ち受けていたソ連製の戦闘機27機を、12機の零戦がわずか10分で全滅させたのです。
国民革命軍の空軍を指揮していたアメリカ人の「シェンノート」は、零戦のデータをアメリカに報告しましたが、「日本人がそんな飛行機を作れるはずがない」と取り合ってもらえませんでした。
ここまで、支那事変がいかに出口の見えない泥沼だったのかを書いてきました。
そんな中、1937年に始まった支那事変もズルズルと1年半ほどが過ぎ、国力を消耗していた日本に追い討ちをかけるかのように、ソ連が動き出すのでした。
しかしどちらも実を結ぶことはありませんでした。
10月には、支那に権益を有する九カ国によって、「ブリュッセル国際会議」が開催されましたが、この会議は「日支和平の仲介」が目的とされていたものの、実際は支那利権を有する国々による「日本の吊るしあげ」にすぎず、それを感じ取った日本は不参加を表明します。
日本は「軍事目的が終了した時期に、公平な第三国による和平の斡旋を受け入れる」という方針を決定し、アメリカ やイギリスなどに伝えます。
日本が考えていた「公平な第三国」とは、ドイツでした。
ドイツは支那に領土的な権益を持たず(第一次世界大戦で日本が引き継いだ)、なおかつ「中独合作」によって中華民国との太いパイプを持っていたのです。
ブリュッセル会議の開催など、世界的に和平交渉を後押しする空気の中、日本はドイツ公使の「オスカー・トラウトマン」を仲介した和平交渉「トラウトマン工作」を進め、11月上旬には正式に蒋介石の国民政府に和平条件7カ条を通知しました。
しかし蒋介石は、開催中だったブリュッセル会議でアメリカやイギリスがより強い圧力を日本にかけてくれるだろうと期待して、この和平交渉には乗りませんでした。
このトラウトマン工作は、支那事変の戦線が拡大しきる前の、唯一にして最大の和平の機会であったと言えますが、蒋介石の思惑によって事変の収集には至りませんでした。
 |
| オスカー・トラウトマン |
しかし、この支那事変に至っても、イギリスは少なからず日本の味方でいました。
ブリュッセル会議において、イギリス大使は本国政府に「日本に対する制裁を議論すべきではない」という旨を上申していたのです。
イギリスは、列強国が集団で日本に圧力をかけて停戦に持ち込むのではなく、あくまでも日本と支那の問題として、第三国を介して和平を結ぶのが望ましいとする日本の考えに理解を示していたのです。
支那において最大の利権を得ていたイギリスは、アメリカの進出を警戒して日本と歩調を合わせようとしていたようにも思えます。
もし、この時に日本が「国際社会の中で孤立せずに強かにやりこなす」という選択肢を持っていたとすれば、その鍵はイギリスが握っていたのではないでしょうか。
しかし、日本が選んだ道はあくまでも、「列強国によるアジア支配に啖呵を切る」というものでした。
その選択を「愚か」だと断じる事も避けたいと思います。
 |
| 支那利権を貪っていたイギリスと、そこに付け入ろうとするアメリカ |
・これ以上支那を追撃する必要はない
・この時期に和平を結ぶのは支那自身の為になる
と訴えかけ、アメリカが和平の斡旋をして欲しいと依頼しました。
当然ながら、アメリカがこの依頼に動くはずもなく、日本軍は南京攻略へと進んでいくことになります。
そして12月、今度は蒋介石が日本との交渉を望んだ為、再びトラウトマンを介した和平工作が行われましたが、すでに日本軍も南京を陥落させて軍事的優位に立っており、さらに多大な損害を被っていた為、それまでのような寛大な条件を提示することはできなくなっていました。(第二次トラウトマン工作)
蒋介石は曖昧な返事でのらりくらりと回答を引き伸ばし、結局両国代表の面会もならぬまま、1938年1月16日、日本政府は交渉打ち切りの声明を出してしまいます。
近衛文麿首相は、「国民政府を対手とせず(国民政府は相手にしない)」と発言し、両国の外交官は帰国、日本と国民政府の国交は断絶されてしまいました。(第一次近衛声明)
両国の和平に奔走した広田弘毅外相は、戦後の東京裁判で「支那事変を拡大させた」としてなぜか絞首刑に処される事になってしまうのでした。
 |
| 広田弘毅外務大臣 |
これによって、国家が人的・物的資源を自由に統制できるようになり、国民の自由意志よりも国家の命令の方の優先される事になりました。
この目的は、「長期化する戦争を乗り切る為に全ての国力を軍需に集中させる事」だったのですが、その発想の根本には「社会主義思想」が見え隠れしていました。
国家総動員法を立案したのは内閣直属の「企画院」ですが、実は企画院内部には共産主義思想が蔓延しており、のちに企画院関係者21名が治安維持法違反で検挙される「企画院事件」が起こっています。
「右傾化すると戦争になる」などと報じて現在のマスコミは「右翼=軍国主義」と言うイメージを刷り込もうとしていますが、日本の戦争体制を築き上げたのは「左翼思想」であったという事実も念頭において頂きたいものです。
蒋介石は日本を広大な大陸に引き込んで「消耗戦」を挑んできたのです。
しかし商工業の要所を抑えられた国民政府に、長期戦に耐えうる国力などなかったはずです。
実は蒋介石は、アメリカ・ソ連・フランス・イギリスなどから多大な軍事支援を得ていました。
支那における軍事行動は、支那利権を持つ欧米列強各国を全て敵に回してしまったのです。
支那事変の実態は、欧米列強が背後に隠れた「代理戦争」であったと言えます。
1938年10月、日本軍が要衝「武漢三鎮」を攻略したところで支那事変の戦況は小康状態に入りました。
重慶は山脈に囲まれた要衝となっており、陸軍が侵攻するのが非常に困難だったのです。
ところで、支那事変において世界を敵に回した日本でしたが、理解者がいないわけではありませんでした。
ローマ法王の「ピウス11世」です。
ピウス11世は日本の軍事行動を支持し、
「日本の行動は、侵略ではない。日本は支那を守ろうとしているのである。日本は共産主義を排除するために戦っている。共産主義が存在する限り、全世界のカトリック教会、信徒は、遠慮なく日本軍に協力せよ」
という声明を全世界のカトリック教徒へ発信しました。
ピウス11世は、平和を乱しているのが共産主義である事をいち早く見抜いていたのです。
しかし、第二次世界大戦が始まる前、1939年に死去したため、その影響力を発揮する事はできませんでした。
 |
| ピウス11世 |
「堅壁清野」という作戦については前回も書きましたが、これは国民革命軍が退却するときに、日本軍が施設を利用できないように村々を焼き払う事です。
その最たるものが「長沙焚城」です。
1938年11月、日本軍が迫る「長沙」において、「日本軍が来たら火を放つように」と指示をされていた国民革命軍は、長沙城外で火事が起こったのを「のろし」だと勘違いし、次々に放火を始めました。
長沙城内では大火災が起こり、20万人以上の死者が出る大惨事となりました。
 |
| 長沙焚城(文夕大火) |
 |
| 「長沙大火で逃げ遅れた老婆を助ける日本兵」とされている写真 |
他にも、国民革命軍は、日本軍の侵攻を食い止めるため、蒋介石の承認を得た上で黄河の堤防を決壊させました。
これによって黄河の水は堤防の外に流出し、少なくとも数十万以上の水死者が出ました。(一説には100万人とも)
日本軍には犠牲者や損害はほとんどなく、むしろ積極的に現地支那人の救助活動を行なっていたようです。
日本軍と住民達が共同で防水作業をしている所に、国民革命軍は容赦なく攻撃を仕掛けました。
また、国民革命軍は黄河のみならず、揚子江でも同じように堤防を決壊させて大規模な水害を起こしています。
このような国民革命軍の蛮行は、支那の住民達からの反感を買い、国民党の求心力は失われていくことになり、後に共産党に支那の覇権をとって変わられる原因となるのです。
さて、戦況が膠着した後、日本が攻略した地域では治安が維持されるようになり、自治政府ができるようになりました。
国民党のナンバー2であった「汪兆銘(おう ちょうめい)」は、支那事変における国民革命軍の横暴によって苦しむ民衆の被害に心を痛め、日本との和平を望むようになります。
「長沙焚城」を明確に批判した事によって、蒋介石との溝は決定的になっていました。
 |
| 汪兆銘 |
一向に事変収集の目処が立たない近衛内閣も「国民政府を対手とせず」という近衛声明を修正し、11月3日に「第二次近衛声明」を発表します。
この声明は、欧米に対抗すべく日本・支那・満州で経済ブロックを形成しようとする、アジアの自存自衛の為の構想「東亜新秩序」を謳ったものでした。
 |
| 近衛文麿 |
これを受けて、汪兆銘は国民党から命を狙われながらも重慶を脱出します。
しかし近衛首相は、12月22日に「善隣友好」「共同防共」「経済提携」の「近衛三原則」を発表し、支那との和平方針を示し「日本軍の撤兵」を外してしまいました。(第三次近衛声明)
この声明の中に、「日本軍の撤兵」が含まれていなかった事に汪兆銘は失望を隠せず、さらに近衛文麿首相は、第三次近衛声明の数週間後に突然総辞職してしまいます。
近衛内閣の後を継いだのは「平沼騏一郎(ひらぬま きいちろう)」を首相とする平沼内閣です。
 |
| 平沼騏一郎 |
 |
| 汪兆銘政権 |
しかし汪政権である南京国民政府の誕生にも関わらず、日本や汪兆銘が意図したように、蒋介石の「重慶国民政府」との和平実現に繋がる事はなく、南京国民政府は国際的には「日本の傀儡政権」に過ぎませんでした。
汪兆銘は過去に狙撃された時の傷が原因で1944年に死去する事になります。
命をかけて日本との和平を模索した汪兆銘は「漢奸(売国奴)」とみなされ、墓を爆破されて遺体を燃やされ、野原に捨てられてしまいました。
汪兆銘は墓を爆破された代わりに石像が建てられましたが、この石像は弔いの意味を持つものではなく、「唾を吐きかける」為でした。
「死者に鞭を打つ」という文化には、全く理解の余地がございません。
 |
| 汪兆銘夫妻がひざまづく姿の裸像 |
しかし重慶への道のりは遠く険しく、陸軍の進軍は困難であるとされました。
そこで航空機による爆撃で重慶国民政府の戦略中枢を破壊する事になり、1938年から1943年にかけて218回の爆撃が行われました。
この爆撃による死者の総数は1万人を超えるとされており、現代においては「無差別爆撃の原型」だと非難され、後に日本全土が空襲で焦土化された事も「重慶爆撃の報い」などと考える人(NHK)もいます。
日本軍の資料を公平な目線で紐解いてみれば、初期の爆撃は間違いなく「無差別爆撃」ではなく、「戦略爆撃」であり、爆撃対象は飛行場や軍事施設に限られていました。
しかし重慶には市街地に相当数の高射砲が設置されており、日本軍爆撃機にも多大な損害が出ていました。
その為、1940年の後半からは市街地を5つに区分し、地区別に絨毯爆撃を行うことになったのです。
日本軍は律儀にビラを撒いて爆撃予告をしていた為、大した戦果は得られなかったようです。
当時の重慶の人口は100万人、218回の爆撃で1万人の死者が出ていますが、これを日本の同規模の都市が受けた空襲の被害と比べてみると、「熱田空襲」では一回の空襲で2000名、神戸では二回の空襲だけで8000名、横浜では一回の空襲で一万人が死亡しています。
数字だけを見ても、日本軍が行った重慶爆撃と、アメリカが日本に行った空襲とでは、「やり方そのものが全く違う」のだと認識できます。
「日本が先に無差別爆撃を行ったのだから、空襲を受けたのは因果応報だ」というような論調には全く同意できないのであります。
 |
| 日本軍の爆撃から逃れる為に豪に避難したものの、多くの人が圧死、窒息死しました |
1940年、最大速度・武器・航続距離・上昇機能・旋回性能、全てにおいて外国の一流機の水準を超えた戦闘機が開発されました。
その機体は、皇紀2600年の「00」にちなんで「零式艦上戦闘機(零戦)」と名づけられます。
それまでの戦闘機では航続距離が足らず、重慶まで爆撃機を援護することができずに多大な損害を出していた日本軍爆撃機も、零戦によって護衛される事になりました。
零戦の初出撃は非常に華々しい戦果をあげる事になります。
重慶で待ち受けていたソ連製の戦闘機27機を、12機の零戦がわずか10分で全滅させたのです。
国民革命軍の空軍を指揮していたアメリカ人の「シェンノート」は、零戦のデータをアメリカに報告しましたが、「日本人がそんな飛行機を作れるはずがない」と取り合ってもらえませんでした。
 |
| クレア・リー・シェンノート |
ここまで、支那事変がいかに出口の見えない泥沼だったのかを書いてきました。
そんな中、1937年に始まった支那事変もズルズルと1年半ほどが過ぎ、国力を消耗していた日本に追い討ちをかけるかのように、ソ連が動き出すのでした。